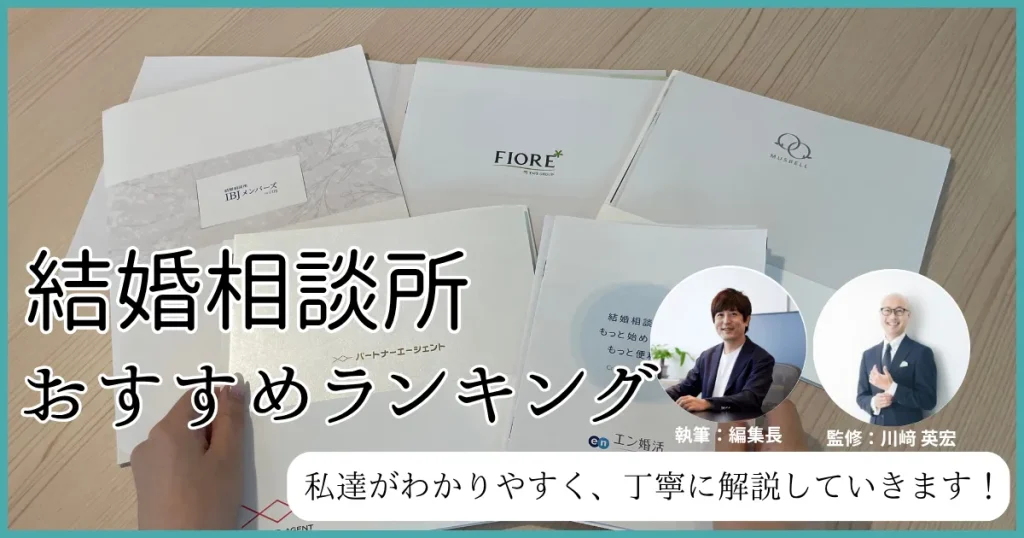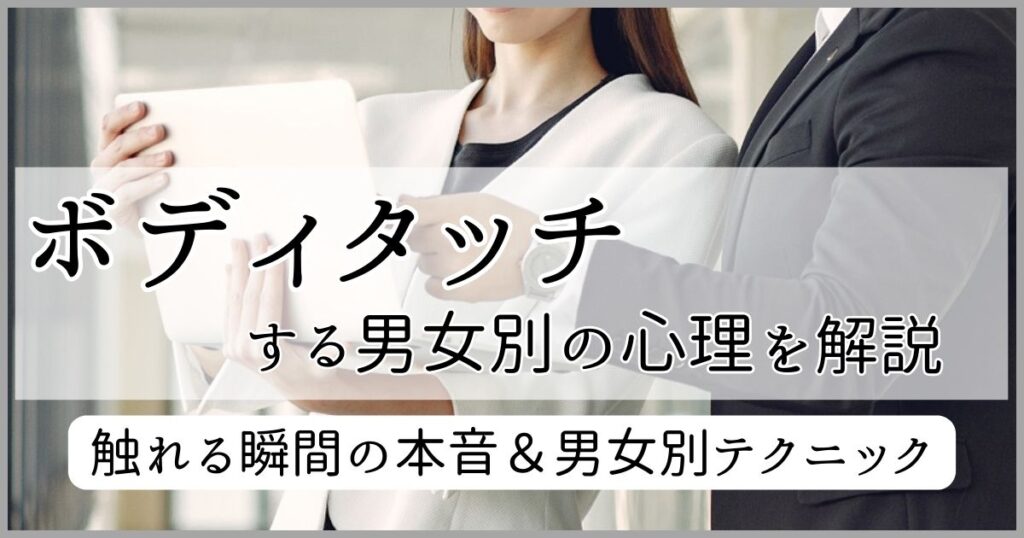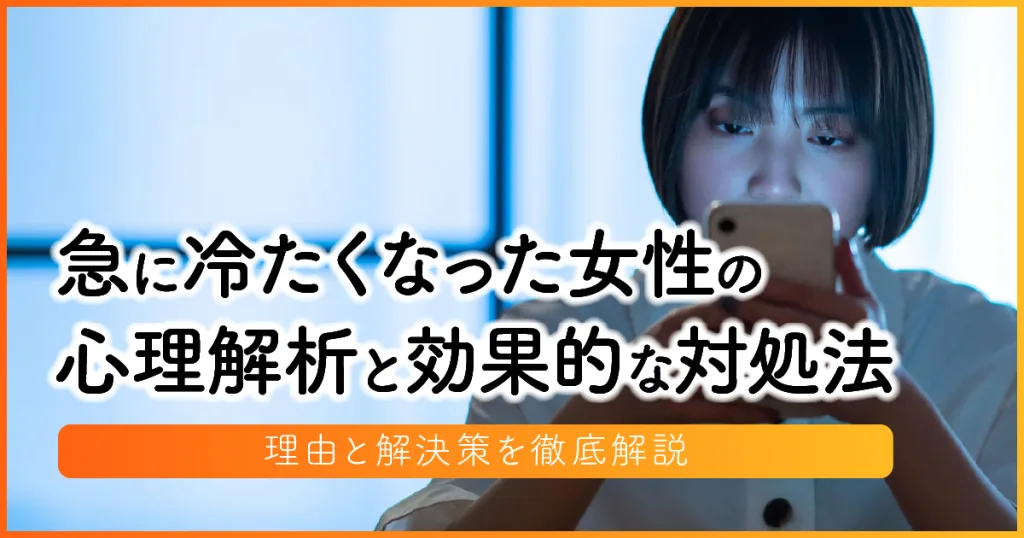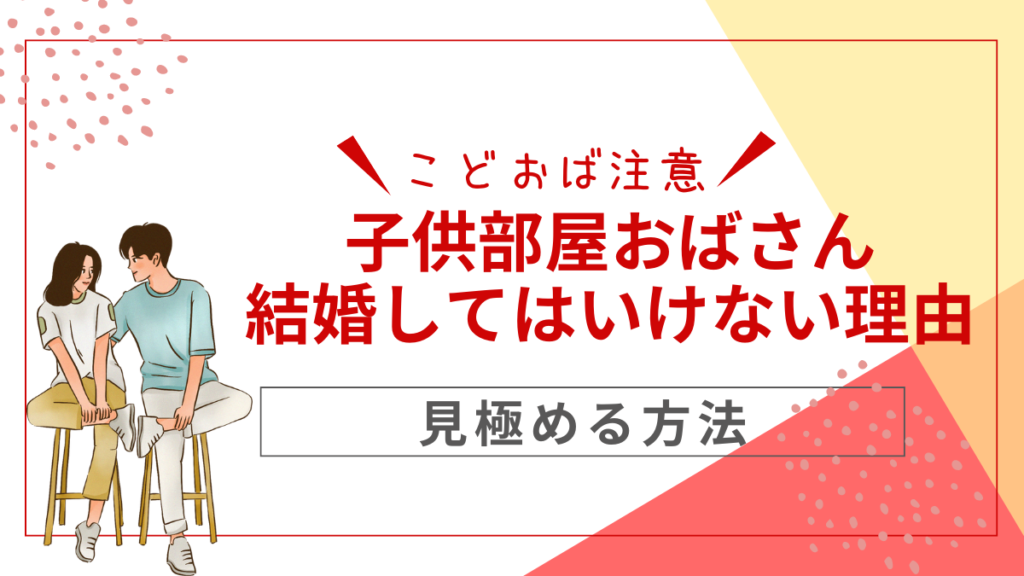このページは広告を含みますが、選定は編集部が公平に行っています。詳しくはポリシーをご覧ください。
子連れ再婚の離婚率は高い?統計データと100人以上の声から見えた、幸せな家族を築くための知識を解説

「子連れで再婚したいけれど、また離婚してしまったら…」
「新しいパートナーと子どもの関係はうまくいくのだろうか…」
大切なお子さまのことを想うからこそ、再婚に対して慎重になり、このような不安を抱えていらっしゃる方は少なくありません。巷では「子連れ再婚は離婚率が高い」という話を耳にすることもあり、一歩を踏み出す勇気が持てずにいる方もいるのではないでしょうか。
こんにちは。「婚活パラダイス」編集部です。
私たちはこれまで、大学教授や恋愛・結婚の専門家36名以上、結婚相談所の事業者52社、そして100件を超える婚活当事者の方々へインタビューを重ねてきました。その中で、子連れ再婚ならではの悩みや課題、そして、それを乗り越えて幸せな家庭を築いている方々の声を数多くお聞きしてきました。
この記事では、公的な統計データを基に「子連れ再婚の離婚率」の真実に迫るとともに、私たちが取材を通して得たリアルな声を踏まえ、子連れ再婚で起こりがちな問題とその解決策、そして幸せなステップファミリーになるための具体的な方法を徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたの心の中にある漠然とした不安が解消され、前向きな一歩を踏み出すための具体的なヒントが得られているはずです。

執筆:佐藤祐介
婚活パラダイス運営のLIFRELL代表取締役。自ら婚活や恋愛に関する専門家へインタビュー取材、インタビュー数35名以上、また結婚相談所へのインタビュー、利用者へのインタビューは100本以上実施。専門家から得られた知識を記事に反映しています。

編集:婚活パラダイス編集部
婚活や結婚相談所、マッチングアプリなど、多様な出会いの形をサポートするために、正しい情報と実践的なノウハウを発信することを目指しています。年齢や性別を問わず、すべての方が自分らしい出会いを楽しめるよう、専門家や経験豊富なアドバイザーの知見を取り入れながら、信頼できる情報をわかりやすくお伝えしています。▷著者プロフィールを見る
\おすすめ結婚相談所/
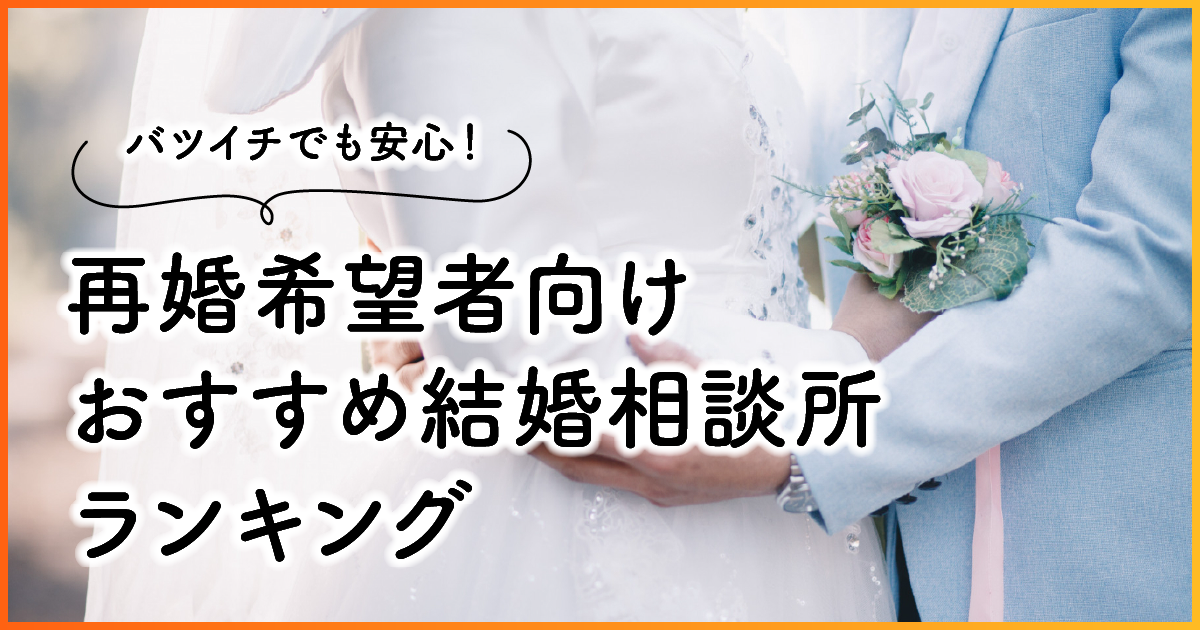

子連れ再婚の離婚率は46%?気になる統計データの真実と向き合う
子連れ再婚を考える上で、多くの方が最も気になるのが「離婚率」ではないでしょうか。具体的なデータを見ることで、現状を正しく理解し、対策を立てることができます。
「再婚同士」の離婚率は初婚より高い傾向にある
まず、厚生労働省が公表している人口動態調査を見てみましょう。
残念ながら、「子連れ再婚」に限定した離婚率の公式な統計データは存在しません。しかし、夫婦のどちらか、または両方が再婚である場合の離婚率は、初婚同士の夫婦よりも高い傾向にあることがわかっています。
以下の表は、婚姻した年ごとの夫婦が、その後5年以内に離婚した割合を示したものです。
【婚姻後5年以内の離婚率の比較】
| 婚姻の種類 | 2015年に結婚 | 2010年に結婚 |
| 夫婦ともに初婚 | 7.9% | 9.7% |
| 夫婦どちらか・または両方が再婚 | 17.2% | 19.3% |
このデータを見ると、再婚夫婦の離婚率は初婚夫婦のおよそ2倍となっており、決して低い数字ではないことがわかります。
さらに、アメリカの統計ではありますが、「子連れ再婚(ステップファミリー)の離婚率は60〜70%にのぼる」というデータも存在します。文化や社会背景が違うため一概には言えませんが、子連れ再婚には特有の難しさがあることを示唆していると言えるでしょう。
なぜデータと向き合うことが大切なのか
このような数字を見ると、不安に感じてしまうかもしれません。しかし、大切なのは、いたずらに不安を煽ることではなく、「なぜ離婚率が高くなる傾向にあるのか」その原因を正しく理解し、事前に対策を講じることです。
データはあくまでも全体的な傾向を示すもの。一つ一つの家族には、それぞれの物語があります。これから解説する離婚の原因や成功の秘訣を知ることで、あなたは統計上の数字を乗り越え、幸せな家族を築くことができるはずです。私たち婚活パラダイス編集部が取材してきた中でも、困難を乗り越え、笑顔あふれる毎日を送っているステップファミリーはたくさんいらっしゃいます。
なぜ?子連れ再婚で離婚に至ってしまう5つの大きな原因
では、なぜ子連れ再婚は離婚に至るケースが少なくないのでしょうか。100人以上の利用者インタビューや専門家の意見から見えてきた、代表的な5つの原因を解説します。これらは、再婚前にパートナーと必ず話し合っておくべき重要なポイントです。
原因1. 「子ども」と「新しい親」の関係がうまくいかない
最も多く、そして根深い原因が、お子さまと新しいパートナーとの関係です。一言で「うまくいかない」と言っても、その状況は様々です。
子どもが懐かない、反抗する
特に物心がついているお子さまの場合、新しい親を「パパ(ママ)を奪った人」と敵視してしまったり、名字が変わることや環境の変化に戸惑い、反発したりすることがあります。
新しい親が子どもとの関わり方がわからない
自分の子どもではないため、どこまで踏み込んで叱っていいのか、愛情表現はどうすればいいのか、距離感に悩んでしまうケースです。良かれと思ってしたことが、裏目に出てしまうこともあります。
実親(子どもの立場)が板挟みになる
子どもとパートナー、両方の気持ちを尊重しようとするあまり、どちらの味方もできず、精神的に追い詰められてしまうことも。
編集部の視点
私たちがインタビューした方の中には、「焦って”お父さん”になろうとしすぎた」と語る男性がいました。彼は、早く子どもに認められたい一心で、厳しく躾をしたり、積極的に関わろうとしたりしましたが、結果的に子どもの心を閉ざさせてしまったそうです。
大切なのは、「親になろう」と気負うのではなく、まずは「信頼できる大人」として、子どものペースに合わせてゆっくりと関係を築く視点なのかもしれません。
原因2. 元パートナーとの関係が整理できていない
離婚したとはいえ、お子さまにとっては唯一無二の親です。元パートナーとの関係が、再婚後の生活に影を落とすことがあります。
養育費の支払いや面会交流でのトラブル
養育費の支払いが滞ったり、面会交流の頻度や方法を巡って意見が対立したりすると、それが夫婦喧嘩の火種になります。
元パートナーへの嫉妬や不信感
新しいパートナーが、あなたが元パートナーと連絡を取り合うことに嫉妬したり、「まだ未練があるのでは?」と不信感を抱いたりするケースです。
子どもが元パートナーと再婚相手を比べてしまう
子どもが「前のパパ(ママ)の方が良かった」といった発言をすることで、新しいパートナーが傷つき、関係がぎくしゃくすることもあります。
原因3. 「夫婦」よりも「親子」を優先してしまう
お子さまを第一に考えるのは当然のことです。しかし、そのあまり、夫婦としてのコミュニケーションが希薄になってしまうと、夫婦関係に亀裂が入り始めます。
夫婦二人の時間がない
「子どもが寝た後は疲れてすぐ寝てしまう」「休日はいつも子ども中心の予定」など、夫婦でゆっくり話す時間がなく、いつの間にかすれ違いが生じてしまいます。
悩みを一人で抱え込んでしまう
「パートナーに心配をかけたくない」「子どものことでこれ以上負担をかけられない」と、子育ての悩みや不安を一人で抱え込み、孤立してしまうケースも少なくありません。
「親」と「パートナー」の役割のバランスが崩れる
新しいパートナーが、「自分はただの同居人で、ATMなのではないか」と感じてしまうなど、夫婦間での役割認識にズレが生じることがあります。
原因4. お金に関する価値観のズレや経済的な問題
生活の基盤であるお金の問題は、夫婦関係にダイレクトに影響します。
養育費や生活費の負担
誰が、何を、どれくらい負担するのか。特に、再婚相手の収入で、連れ子の養育費をまかなうことに対して、不満が生まれやすいポイントです。
お金の使い方に対する価値観の違い
子どもの教育費、習い事、お小遣いなど、どこにお金をかけるかの価値観が違うと、度々衝突することになります。
将来のための貯蓄計画
老後の資金やマイホーム購入など、将来のライフプランについて共通認識が持てないと、経済的な不安から関係が悪化することもあります。
原因5. 周囲(特に両親・親族)からの無理解や干渉
当人同士は納得していても、周囲、特に双方の両親や親族が子連れ再婚に反対したり、口を挟んできたりすることがあります。
「子どものために再婚はすべきでない」という反対
孫の将来を案ずるあまり、再婚そのものに反対されるケースです。
孫(連れ子)への接し方の違い
新しいパートナー側の親族が、連れ子に対してどう接していいか分からず、よそよそしい態度をとってしまったり、逆に過干渉になったりすることがあります。
前回の離婚原因を蒸し返される
「また同じ失敗をするのではないか」と、過去の離婚原因を持ち出され、精神的なプレッシャーを感じることもあります。
子どもの年齢別|子連れ再婚で直面しやすい壁と乗り越え方
お子さまの年齢によって、再婚を受け入れるまでにかかる時間や、直面する課題は大きく異なります。ここでは、子どもの年齢別に、具体的な「壁」と、それを乗り越えるためのアプローチ方法を解説します。
【子どもの年齢別|課題とアプローチ方法】
| 年齢 | 主な特徴と課題 | アプローチのポイント |
| 乳幼児期(0〜5歳) | ・新しい親を受け入れやすい ・物心ついた時に「実の親ではない」と知る ・生活リズムの変化に敏感 | ・愛情をたくさん注ぎ、安心できる環境を作る ・実の親の存在を隠さず、適切な時期に伝える準備をしておく ・焦らず、子どものペースに合わせる |
| 学童期(6〜12歳) | ・「本当のパパ(ママ)じゃない」という意識 ・学校での友人関係(名字が変わるなど) ・新しい親の躾への反発 | ・「親」になろうとせず、まずは良き理解者を目指す ・学校の先生と連携し、子どもの様子を気にかける ・叱る役割は実親が中心となり、新しい親は褒める ・見守る役割を意識する |
| 思春期(13歳〜) | ・最も多感で難しい時期 ・新しい家族への強い反発、無視 ・自分のアイデンティティや将来への不安 | ・子どものプライバシーや意思を最大限尊重する ・無理に関係を築こうとせず、時間をかけて見守る姿勢が重要 ・第三者(カウンセラーなど)の力も検討する |
乳幼児期(0〜5歳)の場合
この時期の子どもは、新しい環境や大人への順応性が比較的高く、愛情を注いでくれる大人を自然に親として受け入れることが多いです。しかし、「パパ(ママ)」と呼んでくれていても、安心するのはまだ早いかもしれません。
乗り越えるためのポイント
大切なのは、「いつか真実を伝える」という覚悟を夫婦で共有しておくことです。子どもが成長し、「自分はどこから来たの?」と疑問を持った時に、誠実に答えられるよう準備しておきましょう。また、実の親のアルバムを見せたり、ポジティブな思い出を話して聞かせたりすることで、子どもは自分のルーツを肯定的に受け入れやすくなります。
学童期(6〜12歳)の場合
物事が理解できるようになり、「本当の親ではない」という事実と向き合い始める時期です。学校で名字が変わることをからかわれたり、友人関係に悩んだりすることもあります。新しい親からの躾に「あなたに言われたくない」と反発することも増えるでしょう。
乗り越えるためのポイント
この時期は、「焦らないこと」が何よりも重要です。新しい親は、すぐに「お父さん」「お母さん」になろうとするのではなく、まずは「信頼できるナナメの関係の大人」を目指しましょう。
一緒にゲームをしたり、趣味の話をしたり、勉強を教えてあげたり…。子どもが心を開いてくれるまで、根気強く関わり続ける姿勢が大切です。叱る役割は実親が担い、新しい親は子どもの逃げ場や相談相手になってあげる、といった役割分担も有効です。
思春期(13歳〜)の場合
最も対応が難しいのが思春期です。自我が確立し、親からの干渉を嫌うこの時期に、新しい家族を受け入れることは、子どもにとって非常に大きなストレスとなります。無視されたり、反抗的な態度を取られたりすることも覚悟しておく必要があるかもしれません。
乗り越えるためのポイント
「子どもの領域に踏み込みすぎないこと」、そして「一人の人間として尊重すること」が鉄則です。無理に会話をしようとしたり、家族行事への参加を強制したりするのは逆効果。
まずは、「あなたの味方だよ」というメッセージを伝え続け、そっと見守る姿勢を貫きましょう。挨拶を交わす、食事を一緒に摂るなど、最低限のルールを決めるのも良いでしょう。時間が解決してくれる部分も大きいと信じ、夫婦で支え合いながら、嵐が過ぎ去るのを待つ覚悟が必要です。
幸せなステップファミリーになるために|再婚前に確認すべき7つのチェックリスト
「こんなはずじゃなかった…」という後悔をしないために、再婚というゴールに飛びつく前に、立ち止まって確認すべきことがあります。以下の7つのチェックリストを、ぜひパートナーと一緒に確認してみてください。一つでも「いいえ」がある場合は、結論を出す前にもう少し時間が必要です。
- 【子どもの気持ち】子どもの気持ちを最優先に考え、再婚について話しましたか?
- 子どもが再婚に前向きでなくても、その気持ちを受け止め、不安を取り除く努力をしましたか?
- 「子どもが小さいから大丈夫」と決めつけていませんか?
- 【交流の時間】子どもとパートナーが二人きりで過ごす時間を十分に設けましたか?
- あなたがいない場所で、二人がどんな関係性を築けているか確認しましたか?
- 数回会っただけで「仲が良いから大丈夫」と判断していませんか?
- 【育児方針】お互いの育児や教育に関する方針を具体的に話し合いましたか?
- 「ゲームは1日1時間」「門限は〇時」など、具体的なルールについてすり合わせましたか?
- 躾で意見が対立した時、どうやって解決するか決めていますか?
- 【お金の計画】養育費、生活費、貯蓄など、お金に関する計画を明確にしましたか?
- お互いの収入と支出をオープンにし、家計の管理方法を決めましたか?
- 子どもの将来の学費など、長期的な視点で話し合いましたか?
- 【元パートナーとの関係】元パートナーとの関わり方について、お互いに理解し合っていますか?
- 面会交流の頻度やルールについて、パートナーの理解を得ていますか?
- パートナーは、あなたが元パートナーと連絡を取ることに不安を感じていませんか?
- 【周囲の理解】お互いの両親や親族に紹介し、祝福してもらえそうですか?
- もし反対された場合、どうやって説得していくか二人で考えていますか?
- 周囲の意見に振り回されず、二人で乗り越える覚悟がありますか?
- 【覚悟】「時間をかけてゆっくり家族になる」という覚悟を共有できていますか?
- すぐに理想の家族になれなくても、お互いを責めないと約束できますか?
- 問題が起きた時に、逃げずに二人で向き合い、話し合う覚悟はありますか?
編集部の視点
このチェックリストで最も重要なのは、**「すべてをオープンに話し合うこと」**です。お金のこと、元パートナーのこと、子育てのこと…。これらは、相手に嫌われたくない、気まずくなりたくないという気持ちから、つい曖昧にしてしまいがちなテーマです。しかし、ここで正直に話し合えない関係性は、再婚後に必ず壁にぶつかります。聞きにくいことであっても、愛情があるからこそ、誠実に向き合う勇気を持つことが、幸せな再婚への第一歩です。
再婚後の生活で大切にしたい|家族の絆を深める5つの習慣
無事に再婚を果たした後も、家族の絆を育む努力は続きます。ここでは、幸せなステップファミリーが実践している、今日から始められる5つの習慣をご紹介します。
1. 意識して「夫婦だけの時間」を作る
子ども中心の生活になると、どうしても夫婦の会話は「今日の夕飯どうする?」「〇〇の学校の準備は?」といった事務連絡になりがちです。月に一度でも、数時間でも構いません。
子どもを預けてデートをしたり、二人でゆっくりと将来について語り合ったりする時間を作りましょう。夫婦関係が良好であることが、家庭の安定、ひいては子どもの精神的な安定に繋がります。
2. 「みんな」ではなく「一人ひとり」と向き合う時間を持つ
「家族みんなで」過ごす時間も大切ですが、それと同じくらい「1対1」で向き合う時間も重要です。
- 実親と子どもだけの時間(甘えられる時間)
- 新しい親と子どもだけの時間(二人の関係を深める時間)
これにより、子どもは「自分だけを見てくれている」という安心感を得ることができます。新しい親も、他の家族がいない状況で、子どもとじっくり向き合うことで、新たな一面を発見できるかもしれません。
3. 新しい「家族のルール」をみんなで決める
再婚は、異なる文化を持つ家庭が一つになるということです。食事の作法、休日の過ごし方、お手伝いのルールなど、これまでの「当たり前」が通用しないことも多々あります。
そこで、「〇〇家のルール」を、子どもも交えてみんなで話し合って決めることをお勧めします。子どももルール作りに参加することで、「自分もこの家族の一員だ」という当事者意識が芽生えます。
4. 「ありがとう」と「ごめんね」を言葉で伝える
「言わなくてもわかるだろう」は禁物です。特にステップファミリーでは、お互いが気を遣い合っているからこそ、感謝や謝罪の気持ちを意識して言葉で伝えることが、円滑なコミュニケーションの鍵となります。
- 「いつも美味しいご飯をありがとう」
- 「〇〇君の面倒を見てくれてありがとう、助かったよ」
- 「さっきは言いすぎてごめんね」
小さなことでも言葉にして伝える習慣が、家族の信頼関係を築きます。
5. 「完璧な家族」を目指さない
「理想の父親(母親)にならなければ」「早く本当の家族のように仲良くならなければ」…。そんなプレッシャーは、自分自身を追い詰めるだけでなく、家族にも窮屈な思いをさせてしまいます。
編集部の視点
多くの幸せなステップファミリーに共通しているのは、良い意味での「諦め」と「割り切り」です。血の繋がりがないからこそ、時にはぶつかることもある。
すぐに分かり合えなくて当たり前。そんな風に肩の力を抜き、「まあ、いっか」と笑い飛ばせる余裕を持つことが、長く幸せな関係を続ける秘訣なのかもしれません。時間をかけて、少しずつ、自分たちだけの「家族の形」を作っていけば良いのです。
「養子縁組」はすべき?メリット・デメリットを専門家が解説
子連れ再婚において、法的な親子関係を結ぶ「養子縁組」は、多くの人が一度は考えるテーマです。しかし、そのメリット・デメリットを正しく理解しないまま手続きを進めてしまうと、後々トラブルになる可能性もあります。
養子縁組のメリット
養子縁組をすると、法律上の親子関係が成立します。これにより、様々なメリットが生まれます。
- 法的な親子関係の確立: 戸籍上も親子となり、親権を持つことができます。学校の手続きや病院での同意など、様々な場面で親として対応できます。
- 相続権の発生: 子どもは、養親の財産を相続する権利(法定相続人)を得ます。
- 扶養義務の発生: 養親は子どもを扶養する義務を負い、子どもも将来、養親を扶養する義務を負います。
- 姓(名字)の統一: 親子で同じ姓を名乗ることができ、家族としての一体感が生まれます。
養子縁組のデメリットと注意点
一方で、デメリットや慎重に考えるべき点も存在します。
- 実親との関係: 普通養子縁組の場合、実の親との親子関係も継続します。そのため、実親からの相続権も残りますが、扶養義務も残るため、将来的に複雑な問題が生じる可能性があります。
- 一度結ぶと解消は困難: 養子縁組を解消(離縁)するには、原則として当事者間の合意が必要です。もし相手が合意しない場合は、家庭裁判所での調停や裁判が必要となり、精神的・時間的な負担が大きくなります。
- 子どもの意思の尊重: 最も大切なのは、お子さま自身の気持ちです。特に、ある程度の年齢に達している場合は、養子縁組が何を意味するのかを丁寧に説明し、本人の意思を最大限尊重する必要があります。無理強いは、子どもの心を深く傷つけることに繋がります。
普通養子縁組と特別養子縁組の違い
| 普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
| 実親との関係 | 継続する | 終了する |
| 戸籍の記載 | 養親・実親の名前が記載される | 実親との関係は記載されず、実子と同様の記載 |
| 主な目的 | 家の存続、子の福祉など | 子どもの福祉(実親による養育が困難な場合) |
| 年齢制限 | 原則として15歳未満(15歳以上は本人の同意が必要) | 原則として15歳未満 |
子連れ再婚の場合は、ほとんどが「普通養子縁組」となります。
養子縁組は、家族の形を法的に安定させる有効な手段ですが、決して「愛情の証」や「家族になるための必須条件」ではありません。手続きを急ぐ前に、その法的な意味と影響を夫婦でよく理解し、お子さまの気持ちも踏まえて、慎重に判断することが重要です。
まとめ|焦らず、比べず、自分たちらしい家族の形を
この記事では、子連れ再婚の離婚率に関するデータから、離婚に至る原因、そして幸せなステップファミリーを築くための具体的な方法まで、詳しく解説してきました。
統計データだけを見ると、子連れ再婚の道のりは決して平坦ではないように見えるかもしれません。しかし、その背景にある課題を事前に理解し、パートナーと真摯に向き合い、一つ一つ対策を講じていくことで、乗り越えられない壁はありません。
大切なのは、
- 焦らないこと: すぐに「理想の家族」になろうとせず、時間をかける覚悟を持つ。
- 比べないこと: 他の家族と自分たちを比べず、自分たちらしい幸せの形を見つける。
- 一人で抱え込まないこと: パートナーと何でも話し合い、時には専門家や周りのサポートを頼る。
ということです。
子連れ再婚は、”親二人分”の愛情をお子さまに注ぐことができる、素晴らしいチャンスでもあります。この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、愛するパートナーとお子さまと共に、温かい家庭を築くための一助となれば幸いです。
婚活パラダイスは、子連れ再婚を含め、様々な形での幸せな結婚を目指すすべての方を応援しています。
◆結婚相談所の関連記事
◆恋愛・婚活コラムの関連記事
◆王道のおすすめ結婚相談所
◆年代・目的別のおすすめ結婚相談所
20代におすすめの結婚相談所 | 30代におすすめの結婚相談所 | 40代におすすめの結婚相談所 | 50代・中高年におすすめの結婚相談所 | バツイチ・再婚におすすめの結婚相談所 | おすすめオンライン結婚相談所