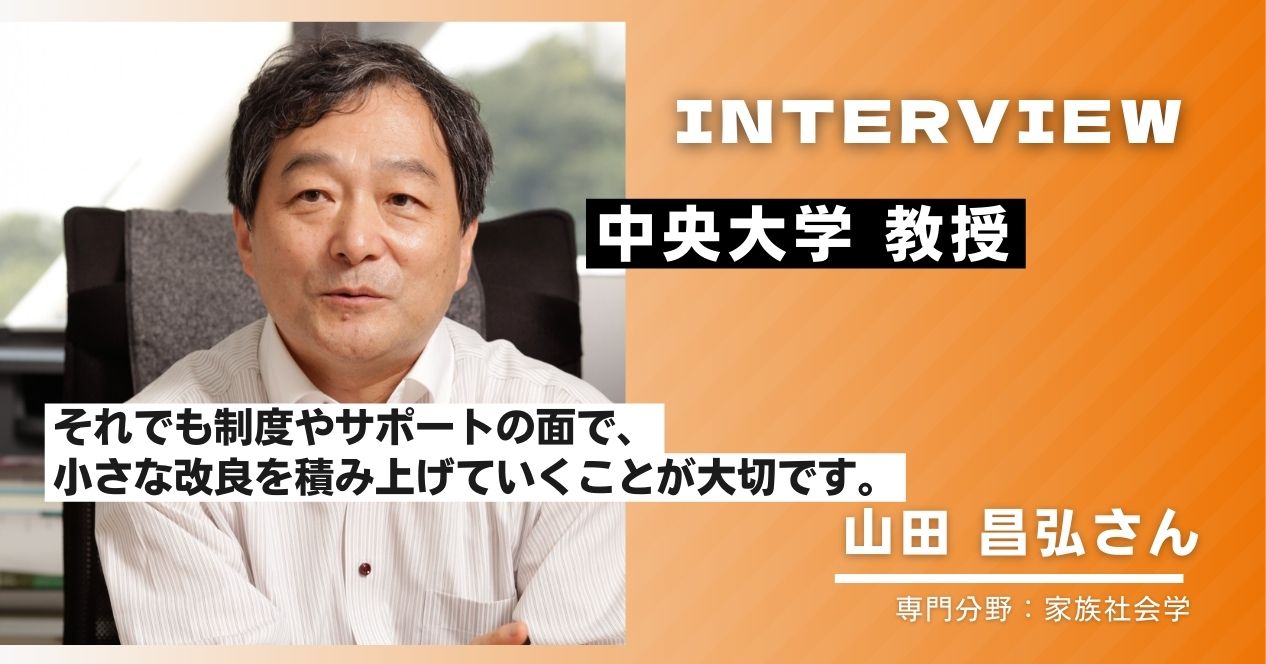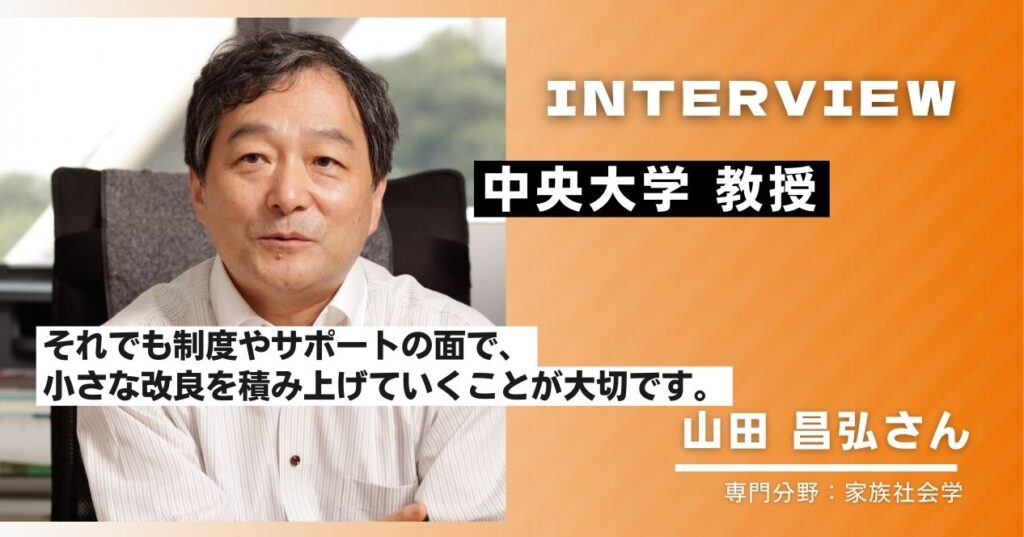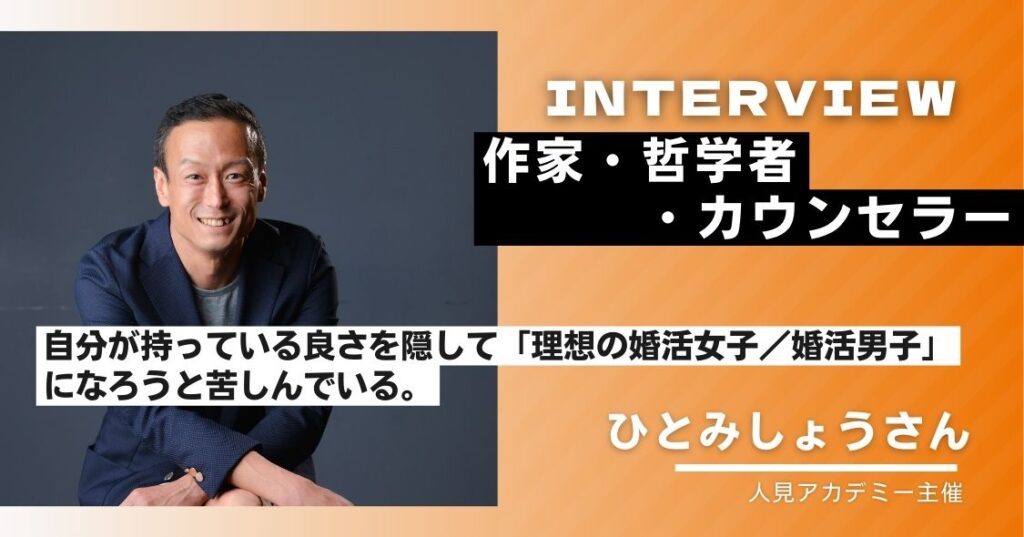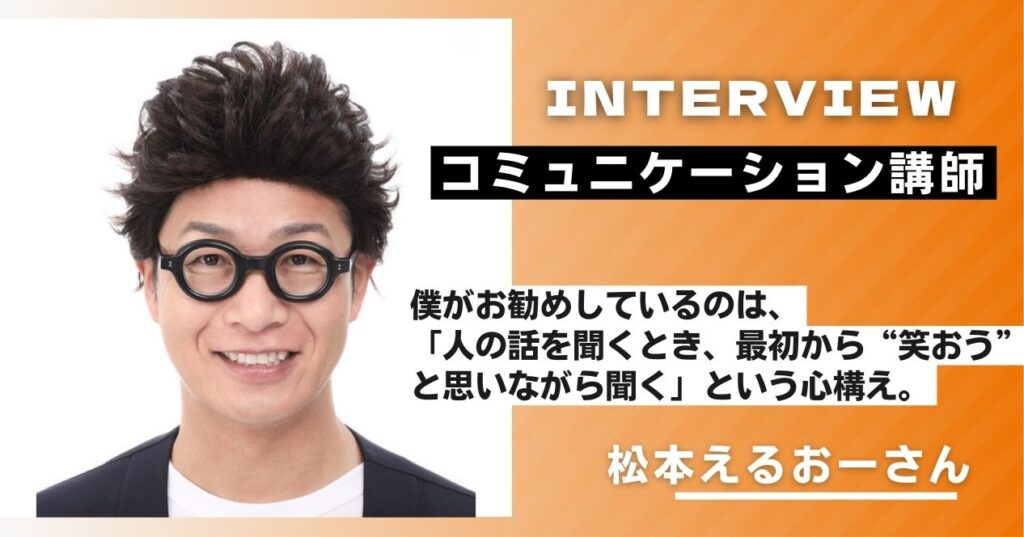出生数70万人割れのニュースが世間を騒がせるなか、「結婚しない・できない」現実は今も根深く社会に横たわります。その解決策は単なる出産支援策にとどまらないと指摘するのは、30年以上にわたり少子化問題を研究する中央大学の山田昌弘教授。
非正規雇用の増加と広がる経済格差から、恋愛観や家族意識に潜む根本的な問題まで――日本の少子化をめぐる最前線を、婚活メディアとして何ができるのか。対談で浮き彫りになった、婚活・結婚の課題と展望をお届けします。

婚活パラダイス編集部 編集長
婚活パラダイス運営のLIFRELL代表取締役。自ら大学教授7名を含む婚活や恋愛に関する専門家へインタビュー取材、インタビュー数36名以上、また結婚相談所の事業者インタビューは52社、マッチングアプリ事業者インタビューは12社、利用者へのインタビューは100件以上実施。専門家から得られた知識を記事に反映しています。▶その他:執筆、編集メンバーはこちら
お問い合わせ:コンタクトフォーム
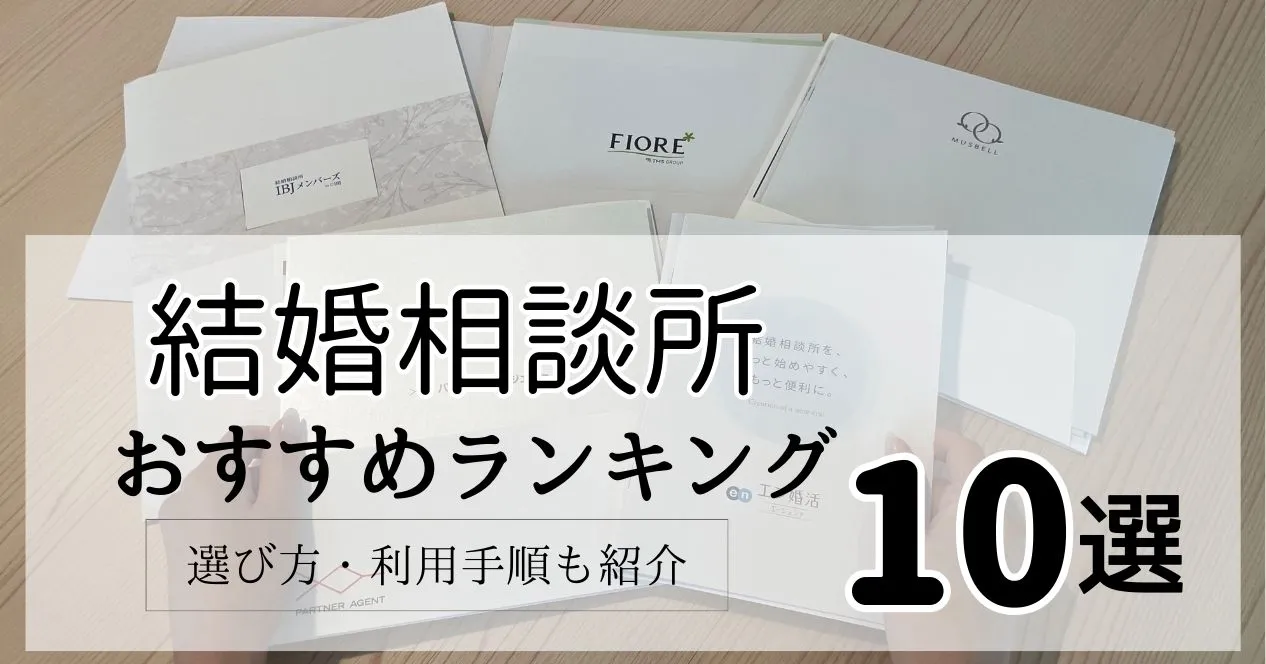
中央大学 教授 山田 昌弘 さん × 婚活パラダイス編集部 インタビュー
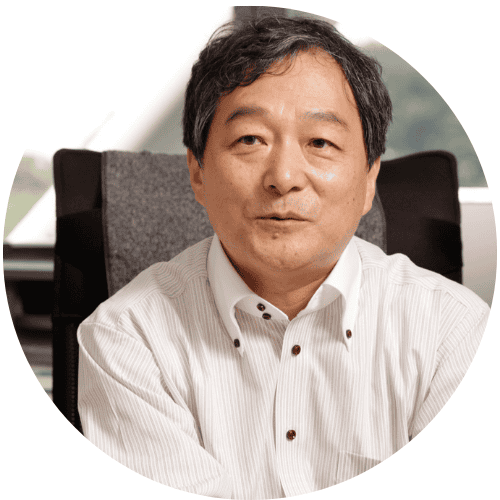
山田 昌弘 さん
中央大学文学部教授。家族社会学・感情社会学・ジェンダー論を専門とし、「パラサイトシングル」や「婚活」「格差社会」など、多くの社会的キーワードを提起してきた第一人者。

少子化に問題意識を持ったきっかけ
――本日はよろしくお願いします。今、自治体と提携して少子化対策や結婚支援、移住支援の情報発信も行っています。先生が少子化に問題意識を最初にもたれたのは、どのような経緯からでしょうか。
もうかれこれ35年ほど前、具体的には1990年前後にはすでに問題意識を持っていました。当時、厚生省(現・厚生労働省)の人口問題に関する研究会に呼ばれたんです。
いわゆる「1.57ショック」(※1)の頃ですね。家族社会学を専門にしていたこともあり、そこから本格的に少子化を研究テーマとして取り組むようになりました。
※1 1.57ショック:1990年に発表された合計特殊出生率が1.57に落ち込み、大きな議論となった出来事。
30年以上続く少子化問題
–先生が問題提起されてから30年以上経ちますが、残念ながら少子化が解消どころか、さらに悪化している印象です。
そうですね。多少の上下はあっても、抜本的に解決していない状況です。出生数が70万人台を割り込むなど、コロナも影響したとはいえ厳しい数字になっています。
— 就職氷河期世代やロスジェネ世代を経て、そのあたりから一層問題が拡大していると感じます。どこからが「決定的な転換点」だったとお考えですか。
1990年代半ばぐらいから、少子化がより加速したと思います。その後ずっと約3/4の人が結婚して子どもを産み、残り1/4が結婚しないという構造が変わらずに来ている。
合計特殊出生率が1.2〜1.5の間で推移してきたものの、未婚率の高さ(特に男性の約4人に1人が生涯未婚)も含め、根本的な部分がほとんど変わっていません。
格差拡大と非正規雇用の増加が結婚に与える影響
–少子化の原因として、非正規雇用の増加や所得の伸び悩みはやはり大きいのでしょうか。
大きいです。経済的安定がないと結婚しにくい、という傾向がはっきりしています。女性側は「どうせ結婚するなら、正社員で安定した収入のある人がいい」と望むケースが多い。
逆に男性も「相手にもある程度の収入を求める」傾向が強まっています。若い世代の格差が拡大すると、経済力がない層同士ではなかなか結婚に踏み切れない。日本だけでなく韓国など東アジアでも似た状況ですね。
政策的な少子化対策の限界と可能性
–政府がやる少子化対策というと、出産一時金や子育て支援などがありますが、それだけではあまり効果がないのではないでしょうか。
正直、それらの支援策は不十分だと思います。例えば、育児休業などの制度も正社員が中心で、パートや自営業者には行き渡らない。
こうした制度の「対象外」が多くなると、かえって格差が広がってしまう可能性もあるわけです。
— 仮に予算を増やしたとしても、ヨーロッパ各国を見ても出生率が2を超える国は少ないですね。
そうですね。移民をたくさん受け入れている国や、もともと恋愛・結婚観が違う社会の場合は、単純比較がしづらい。
東アジアは、「好きだからお金がなくてもいい」とはなりにくい文化です。男性も女性も「ある程度の生活レベルを維持したい」という意識が非常に強い。
それを変えるには雇用制度をはじめ、大きな改革が必要になります。
— 高等教育無償化や保育環境の充実など、いろいろ打ち手はあれど、なかなか抜本的な解決まで至らないということでしょうか。
そうです。一時的に出生率が上がっても1.5前後が限界という見方もあります。もちろんやらないよりはやるほうが良い。
しかし、男性の非正規雇用を減らす、女性が稼ぎやすい社会にするなど、根本的に格差を縮める方向に舵を切らない限り大幅な改善は難しいと考えています。
マッチングアプリや結婚相談所は有効か?
— 弊社では結婚相談所やマッチングアプリの紹介も行っておりますが、どのようにご覧になっていますか。
マッチングアプリは特に条件(年収や職業、年齢)を前面に打ち出しますから、どうしても「スペック重視」になりがちです。
結婚相談所も似た側面がありますね。もちろん、その仕組みで結婚できる人には有効です。
一方で、低収入の人の魅力を引き出すフォローがどこまでできるか。
昔のおせっかいおばさんのように熱心に間に入ってくれる相談所など、例外的にうまくいくケースもあると思いますが、全体を大きく変えるほどではないのが現状でしょう。
地方の少子化と意識・風習の壁
–先生が今注目されているのは地方の少子化問題と伺いました。
はい。女性が大学進学や就職で都市部へ流出することで、地方の少子化はさらに深刻になっています。
一方で東京は保育所が増え、出生率が地方より改善している面もある。
逆に地方は、男性優位・男尊女卑の風習が色濃く残っていたり、女性の就業機会が限られていたりして、ますます若い女性が地元に残りにくい状況です。
— 農村部での婚活イベントなども、まだ「お嫁さん」扱いが当たり前だったり、男性同士だけ飲みに行って女性は家庭内に…という話を聞きます。
収入そのものは農家でも高い人はいるんですが、古い慣習がネックになります。
近年はむしろ「都会へ行って結婚しなさい」という母親も増えている。
そうした風習や地域の体質が変わらないと、地方がどんどん高齢化・人口減少してしまうかもしれません。
今後の展望とまとめ
–最後に、少子化問題はなかなか解決の道筋が見えない部分も多いですが、婚活メディアに携わる私たちや読者へメッセージがあればお願いします。
私自身、30年以上、少子化に関わる議論に携わっていますが、少子化対策は「一朝一夕で成果が出るものではない」と痛感します。
それでも制度やサポートの面で、小さな改良を積み上げていくことが大切です。例えば結婚相談所や自治体の事業でも、きめ細かなフォローがあれば思わぬカップルが成立する可能性はあります。
しかし根幹には「雇用や収入の格差をどう埋めるか」という大問題がある。そこに大胆にメスを入れない限り、大きな数値上の好転は難しいでしょう。
それでも、皆さんのようにメディアで情報発信を続けたり、自治体が真剣に出会いの場を提供したり、と地道な活動を続けることは意味があると思います。
少しずつでも、より良い出会いや結婚が生まれる仕組みづくりを目指していきたいですね。
編集後記
山田昌弘教授のお話から、改めて感じたのは「格差の拡大」が“結婚したくてもできない”状況の深刻さを生んでいる、という点です。恋愛・婚活を取り巻く環境はどんどん多様化しているにもかかわらず、30年以上も未婚率や出生率が大きく改善されていないのは、婚活サービスだけの力ではどうにもならない側面があるからなのでしょう。
その一方で「例外的にうまくいく」事例も確かにあるという指摘は、私たち婚活メディアにも大きな可能性を示唆しています。一人ひとりに丁寧に寄り添う“おせっかい”的なアプローチを、テクノロジーの力と組み合わせていくことで、少しずつでも道は開けるのではないでしょうか。
婚活パラダイスとしても、今後も自治体や専門家と手を携え、より多くの方が前向きな一歩を踏み出せるような情報発信を続けていきたいと思います。