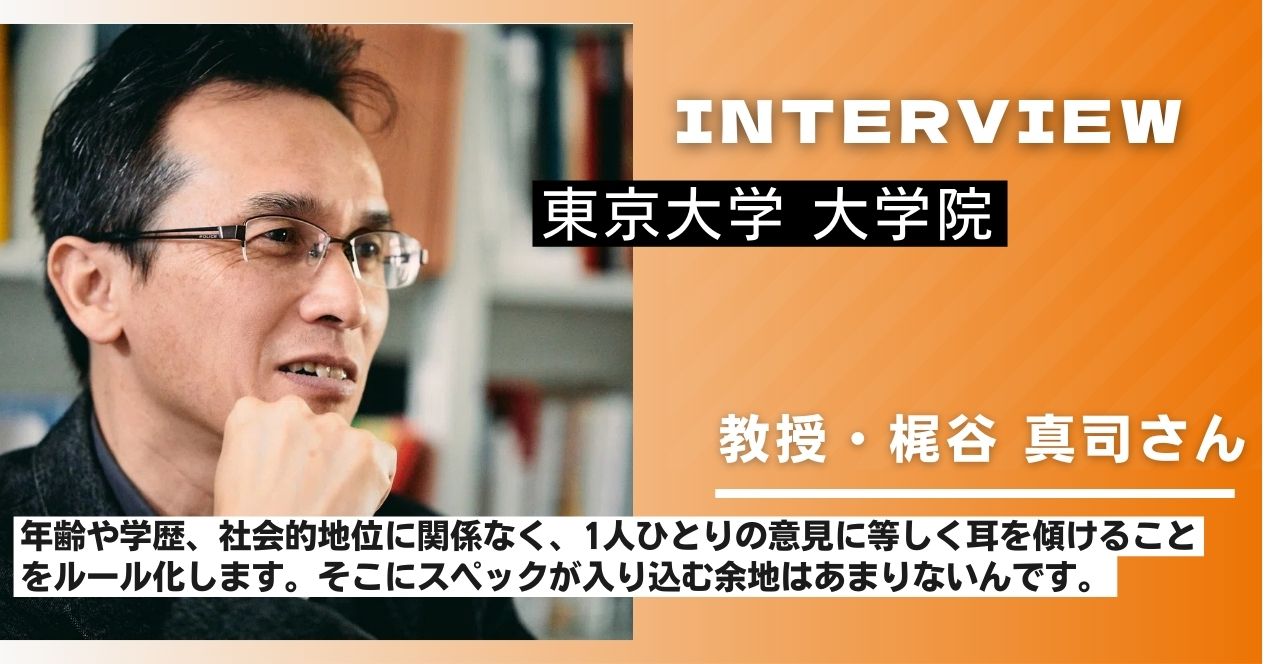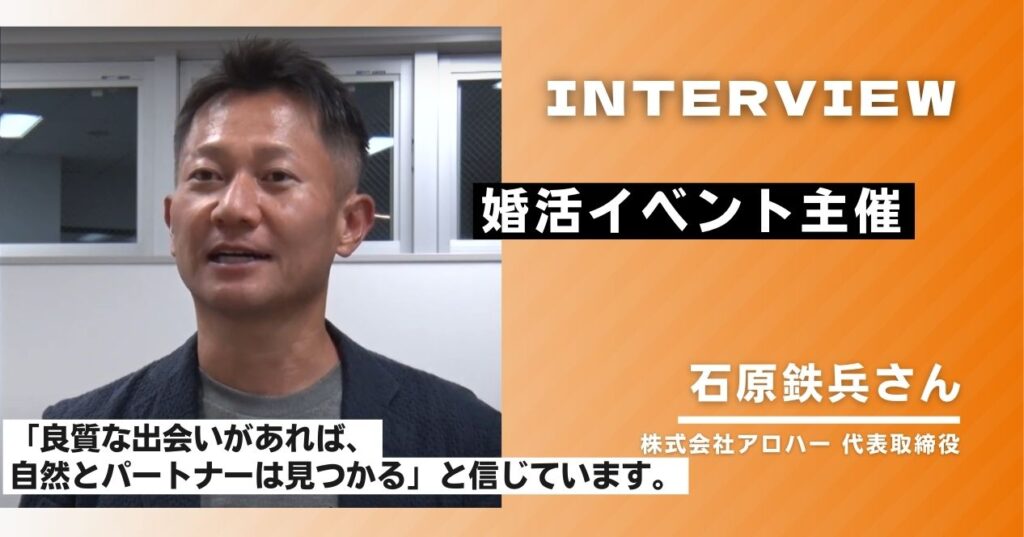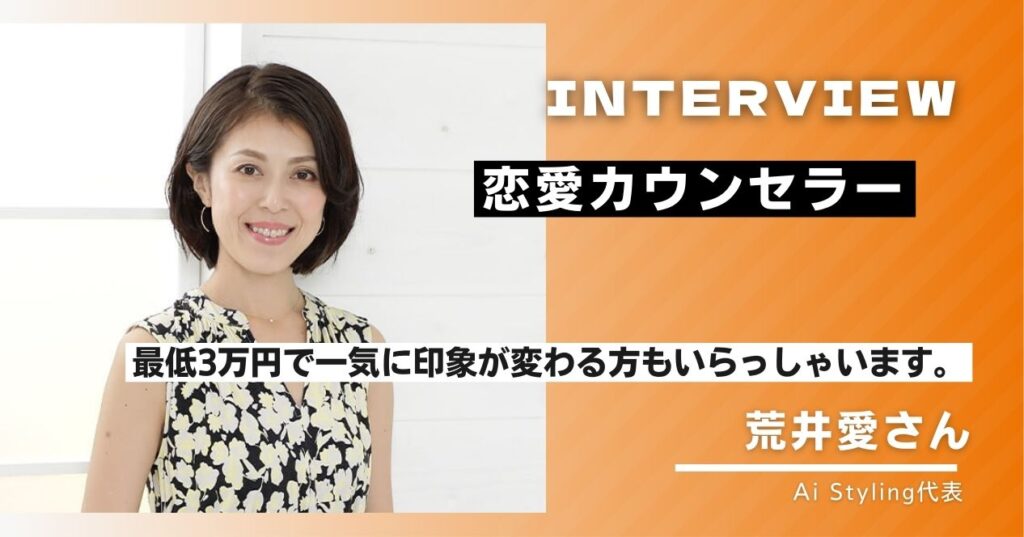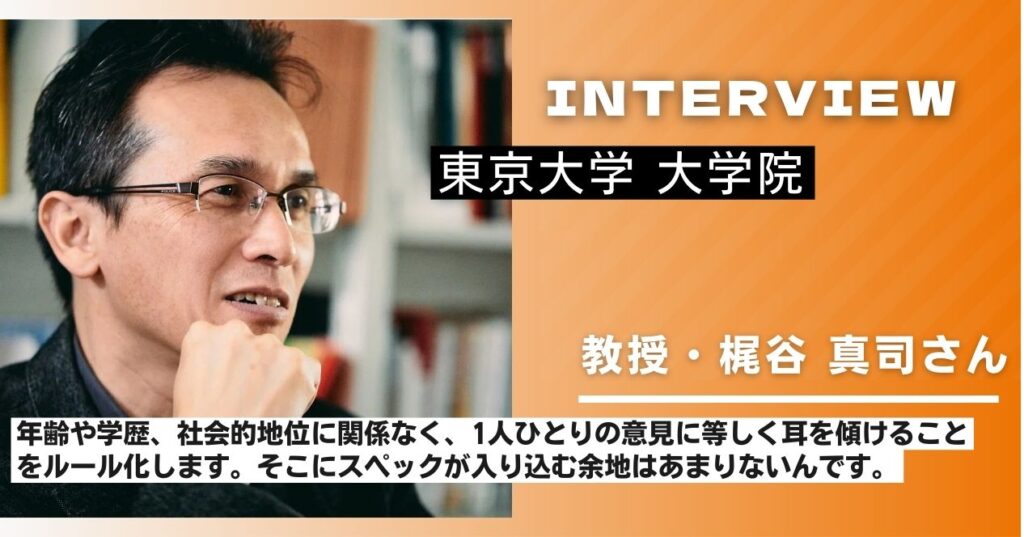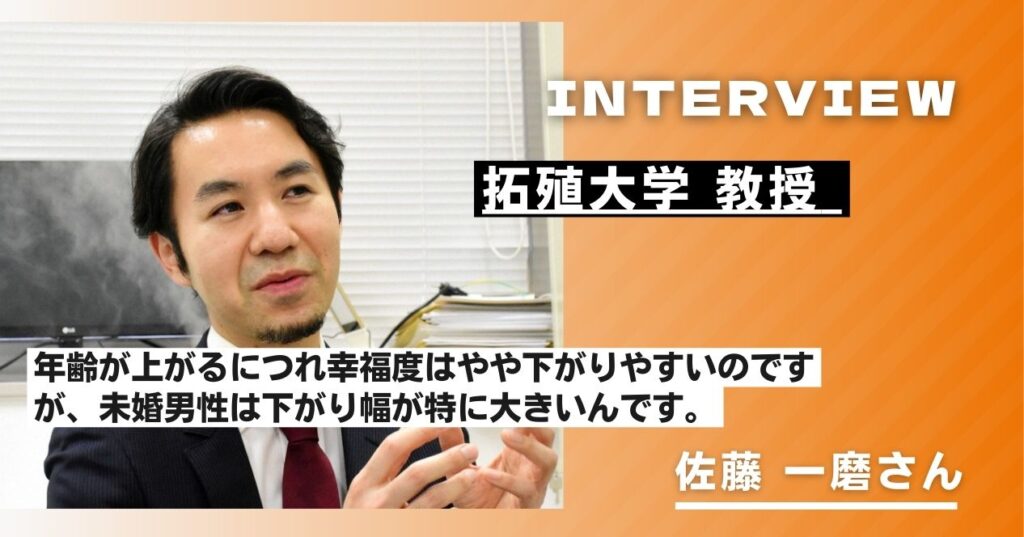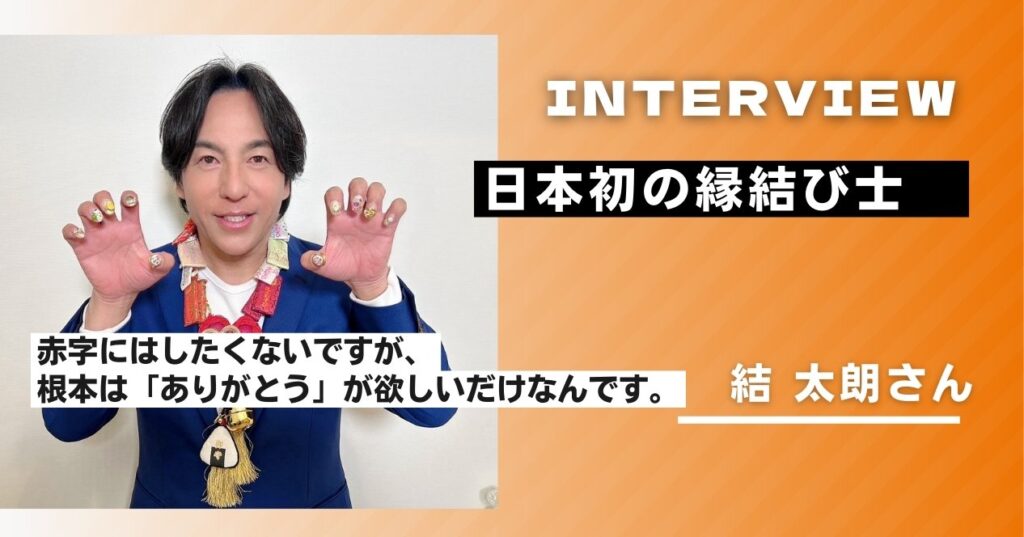いまやマッチングアプリや結婚相談所をはじめ、多様な婚活サービスが登場し、条件やスペックの比較が当たり前のように行われています。
けれども、条件に振り回され続けてもなかなか結婚につながらず、人と深くつながるための“本質的なコミュニケーション”が抜け落ちているのではないでしょうか。
そこで今回、婚活パラダイス編集部は、東京大学大学院 総合文化研究科教授の梶谷 真司(かじたに しんじ)先生にインタビューを実施。
梶谷先生が実践されている「哲学対話」が、実は婚活にも大いに役立つという新しい視点について伺いました。
対話が生む“内面のつながり”こそ、これからの恋愛・婚活に必要不可欠なエッセンスかもしれません。

婚活パラダイス編集部 編集長
婚活パラダイス運営のLIFRELL代表取締役。自ら大学教授7名を含む婚活や恋愛に関する専門家へインタビュー取材、インタビュー数36名以上、また結婚相談所の事業者インタビューは52社、マッチングアプリ事業者インタビューは12社、利用者へのインタビューは100件以上実施。専門家から得られた知識を記事に反映しています。▶その他:執筆、編集メンバーはこちら
お問い合わせ:コンタクトフォーム
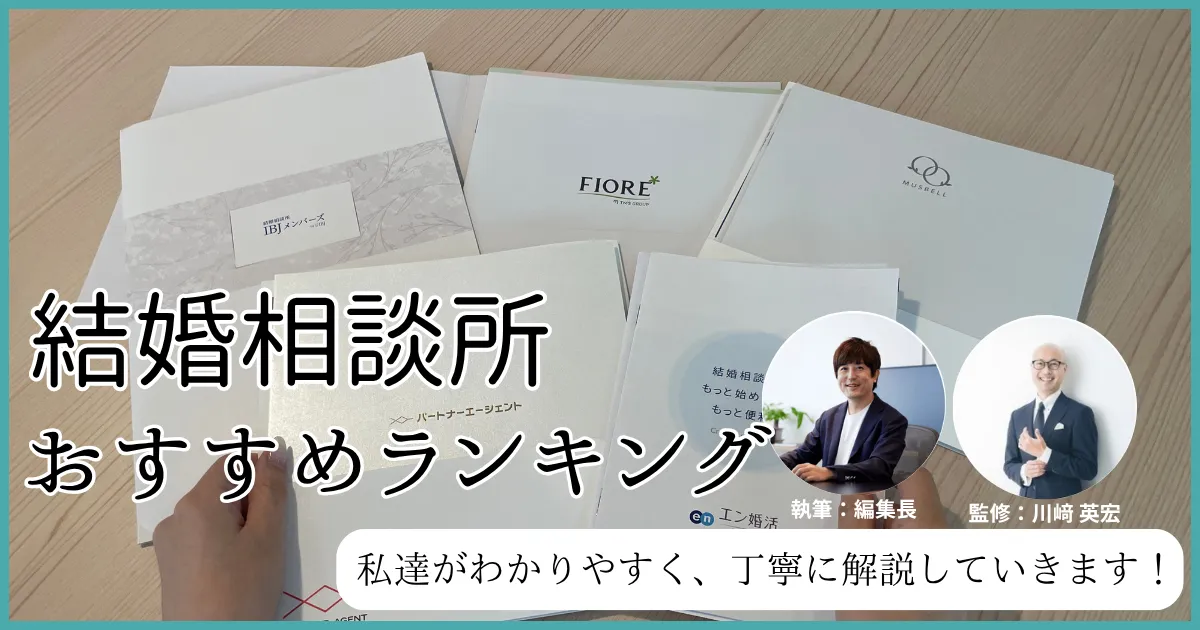
教授・梶谷 真司さん× 婚活パラダイス編集部 インタビュー対談
東京大学 大学院総合文化研究科 教授。京都大学で博士(人間・環境学)を取得し、現象学を基盤に医療史や身体論、教育実践まで幅広く研究。“現実の多元性”の探求を続ける気鋭の哲学者。

出会いのきっかけ──「哲学対話」を婚活メディアが取材する理由
— もともと先生を知ったきっかけは弊社が先日インタビューした株式会社アロハーさん(石原さん)の対談記事に先生のお名前が出てきたことでした。
当メディアは日頃からマッチングアプリや結婚相談所の情報も発信しているのですが、どうしても「年収」「見た目」「所属先」といった分かりやすいスペック比較になりがちで……。
AIが発達したことで、表面的な条件マッチングが逆に強化されているような印象もあります。
一方で、アロハーさんのインタビューにあった「哲学対話」は、薄っぺらいコミュニケーションではなく、深い部分で相手とつながるための手法だと感じたんです。
そこから、ぜひ先生に直接お話を伺いたいと思ってご連絡しました。
こちらこそ、お呼びいただいて嬉しいです。
そもそも「哲学対話」とは?──アメリカの小学校教育から日本各地へ
— そもそも“哲学対話”というと、正直ちょっと難しそうな印象があるのですが、どういう形で始まった手法なのでしょう?
もともとは「子どものための哲学(Philosophy for Children)」というアメリカで始まった教育手法なんですね。
1970年代頃、アメリカで「大学生になってから哲学を学び始めるのでは遅いのでは?」という問題意識があって、小さい頃から「考える力」を育もうとしたのがきっかけです。
といっても哲学書を読むわけではなくて、子どもたちが話し合いながら一緒に深く考える力を養う方法が発展したんです。
それが日本にも2000年代に入ってきて、2010年代くらいから、学校教育だけでなく一般の「哲学カフェ」などで大人向けにも取り入れられるようになってきました。
— 日本でも今、「哲学カフェ」「哲学対話」といったイベントが増えてきていますよね。先生はそれを“婚活”と結びつけてらっしゃるんですよね。
そうなんです。
2012年頃から僕自身はいろんな場で哲学対話をしてきたんですが、ふと「これは婚活にも向いてるんじゃないか」と直感したんです。
実験的に熊本県の上天草市の“街コン”で導入する機会がありやってみたところ、非常に手ごたえがあって。
そこからアロハーさんと一緒にやるようになりました。
婚活に活かす「哲学対話」──スペック比較を超えて“仲良くなる”仕組み
— なぜ婚活で「哲学対話」が有効なのでしょうか?
まず、“人と仲良くなる”プロセスって、基本的には「自分の思いを率直に話す/相手の話をきちんと聞く」の積み重ねじゃないですか。
ところが、一般的な婚活イベントは短い時間で大量の相手を効率よく回そうとする。スペックや条件をまず見てから少し話して、すぐ次にいく……というやり方だと“お互いを知る”ところまで辿りつきにくいんです。
一方、哲学対話では、あらかじめ設定した“8つのルール”に沿って話します。それは、
①何を言ってもいい。
②否定的な発言はしない。
③発言せず、ただ聞いているだけでもいい。
④お互いに問いかけることが大切。
⑤知識ではなく経験に即して話す。
⑥まとまらなくてもいい。
⑦意見や立場が変わってもいい。
⑧分からなくなってもいい。
というものです。
そうすると、率直に自分の思いを語り、相手の話をきちんと聞くということが、自然とできるようになります。
結果的にお互いに内面的につながる場が成立しやすいんですね。
— なるほど。無理やり「内面を見なさい」と言うより、対話しているうちに自然と“中身”が見える、ということですか?
まさにそうですね。
「中身を見なさい」と言われても、どうやれば見られるのか実感がわかないし、逆に意識しすぎるとかえって表面的になってしまう。
哲学対話の流れに身を委ねると、余計な気負いなく話せるので、結果として自然に“お互いの価値観や考え方”が表れてくるんです。
“回転寿司型”パーティーとどう違う?──深い対話が生む充実感
— よくある婚活パーティーやマッチングアプリは、条件で絞って会う・短時間で複数人と話す“回転寿司型”が主流なイメージです。それと比べると、やはり対話重視の方法は相当違いますよね。
違いますね。
回転寿司型だと、一部の人気者に集中してしまって、「モテない層は相手が見つからないまま帰る」というパターンが起きやすい。
一方、哲学対話型の婚活イベントでは、まず一つのグループになって問いを出して、みんなでどれにするか決めます。
そこから10~15人くらいのグループに分かれて、その問いについてじっくり話をします。
最後に「よかったら連絡先を交換してくださいね」というふうに促し、よかったら二次会に行ってくださいと言います。
そうすると、大半の人は「もう少し一緒に話したい」という気持ちになるので、そのまま二次会へ行ったりすることが多いです。
— 二次会で誰とも話したいと思わない……というのは少ないんですね?
むしろほとんどの人が、「もうちょっとこのメンバーでしゃべりたい」となるんですよ。
さらに女性同士が仲良くなって、そのまま友達になるケースも多いですね。「別に結婚につながらなくても価値のある場だった」と思ってくれるわけです。
結果として「満足度が高い」のが哲学対話で行う婚活の特徴だと思います。
“内面を見る”とは具体的にどうする?──“聞く”ことの本当の意味
— 先ほど“8つのルール”に触れられましたが、哲学対話ではどんなことを特に大事にしているのでしょう?
たとえば、「相手の話にすぐ反論や同意を返そうとしなくていい」とか、「沈黙があってもその時間を大事にしましょう」とか。
普通の会話では、つい「次何を言おう」と考えてしまったり、“沈黙は悪”と捉えて急いで埋めようとしたりしますよね。
でも哲学対話だと、その沈黙も「考える時間」として尊重する。
もう一つは「フラットであること」。
年齢や学歴、社会的地位に関係なく、1人ひとりの意見に等しく耳を傾けることをルール化します。
そこにスペックが入り込む余地はあまりないんです。
— なるほど。対話をしているうちに、結果的に相手がどういうことを大事に思っているか、どういう考え方をする人なのかが自然に出てくるんですね。
そうです。
お互いがルールに沿って自分の頭で考えて発言すると、本当にその人らしい意見が出てきますし、相手の中身を見ようと構えなくても、話しているだけで「この人はこういうものの見方をするんだな」って分かってくる。
それが“内面を見る”ということの具体的な姿かもしれません。
ビジネスモデルとしての課題──なぜ普及が難しいのか?
— すごく魅力的なお話なのですが、実はあまり大規模に普及している感じはしません。なにかビジネス上の課題があるのでしょうか?
一番大きいのは「マッチングアプリや従来のパーティー形式のほうが、ビジネスとしては回しやすい」という点です。
AIを使って大量にマッチングさせる、たくさんのフランチャイズ相談所を抱えて月会費を稼ぐ、など大規模化しやすい仕組みがすでに確立していますよね。
でも哲学対話は、人数が多すぎると進行が難しいですし、ファシリテーターをちゃんと配置する必要がある。
回転寿司のように一人ひとり数分で判断するスタイルとは真逆なので、どうしても“効率重視の世界”からは敬遠されがちなんだと思います。
— 「でも参加した人の満足度は高い」のに、ビジネス的には難しい。ジレンマですね。
そうなんです。
だから「じっくり時間をかけてコミュニケーションを楽しみたい」「結婚に限らず人とのつながりを求めている」という層に、もっと知ってほしいし、増えてほしいですね。
結果的にカップルや結婚が生まれればいいし、もしそうならなくても、参加者自身は人生のプラスになる体験ができるはずなので。
学校や企業研修でも活用──対話が作るフラットな関係と驚きの効果
— 実は先生が行われている哲学対話、学校や企業など、さまざまな現場でも取り入れられているとか。
はい、今では学校の授業の中に“哲学対話”を組み込むケースも増えてきました。学習指導要領に「主体的・対話的で深い学び」が目標として掲げられているのも大きいですね。子どもたちがフラットに「自分の考え」を言葉にできる場があると、クラス内の雰囲気が良くなることが多いんです。
また企業研修でも、「上司と部下の壁が厚い」「多様な人材が混ざった結果コミュニケーションがぎくしゃくする」といった問題を抱えているところで、哲学対話を研修に取り入れると、みんな本音で話せる分、信頼関係が生まれやすい。
それまであまり評価されていなかった人が、しっかりした考えを話すので、その人に対する見方が変わったり、気難しい上司が意外に優しいことが分かったり、いろいろ面白い効果があります。
— 学校での話は印象的ですね。“成績が悪い子”や“障がいがある子”が、対話の場ではすごく重要な意見を出していて、周りが驚くこともあるとか。
それがよく起きるんですよ。
実際、偏差値40くらいの生徒がものすごく深い意見を出して、いわゆる勉強ができる子が圧倒される、なんてエピソードもあります。
要は「教科知識を披露する」場とは違うから、そこでは“自分の頭で考えて話す”ことが重視されるんです。
婚活でもやはり同じことが起きて、普段なら見えない一面が引き出されるのが哲学対話の面白さですね。
日本人は思考停止?──“自分の言葉で考える”きっかけとしての対話
— 確かに、日本人は昔から「会話が苦手」「沈黙を嫌う」という指摘がありますが、最近はさらに「思考停止状態」の人が増えている気がします。スペックに頼り切った婚活も、その一例かもしれません。
そうですね。
どうしても学校や社会の中で、「正解を手っ取り早く出すこと」が求められてきた経緯があるので、自分の言葉でじっくり考える習慣が育ちにくい面はあると思います。
さらに、今のコスパ・タイパ重視の時代だと、“深く考えて話す”ことそのものを避ける傾向もあるかもしれません。
でも、実際に哲学対話を体験すると分かるのが「単なるおしゃべりより疲れるけれど、すごく充実感がある」という声が多いこと。
やればやるほどハマる人もいるんですよ。
自分の頭でじっくり考えた末に口にする言葉は、やはり手応えが全然違うし、相手にも伝わりやすいんですよね。
結婚・少子化問題への期待──内面重視の出会いがもたらす未来
— 今、日本は少子化が進んでいて、国や自治体も婚活支援に取り組んでいます。ただ、経済的な補助やスペック中心のマッチングだけでは、うまくいかない現実もありますよね。
そうですね。
もちろん経済的安定も大切ですが、実際にカップルが結婚するかどうかは、それだけでは決まらない。
むしろ哲学対話を通じて“人としての信頼感”を築いた二人のほうが、たとえ年収や外見が変わっても「一緒に生きていこう」と考えられる可能性が高いように思います。
それが、長期的に見れば離婚率を下げたり、子どもを持つことへの前向きな気持ちにつながっていくのではないでしょうか。
— 確かに今、「子どもはコスト」「子育てはデメリットばかり」みたいな感覚が広がってしまっているのも、十分に“話し合う機会”がないからかもしれませんね。
まさに。
子どもを持つことの意味や、子育てで得られる喜びを、ちゃんと話したり考えたりしないまま「お金がかかるし大変」だけで終わってしまっている気がします。
でも、哲学対話のように「そもそも人生や家族ってどういうものなんだろう?」みたいな根本から語り合えれば、自然と「じゃあどういう生き方をしたい?」という話になってきます。
そこから本当の意味で「じゃあ結婚しようか」「子どもを育てようか」っていう選択肢が出てくることもあると思います。
編集後記
今回は東京大学大学院 総合文化研究科の梶谷 真司先生に、“哲学対話”の概念と婚活への応用についてお話を伺いました。
取材前は「哲学対話」と聞くだけで「難しそう」「堅苦しいのでは?」と身構えてしまう部分があったのですが、実際にお話を聞くとむしろ「人間関係をシンプルで豊かにしてくれる仕組み」だと感じます。
特に印象的だったのは、「対話をしているうちに自然と内面が見えてくる」という点。
スペックや条件を“最初から”比べてしまうと、相手の本当の魅力や自分の価値観との相性を確かめる前に「なし」判定を下してしまいがちです。
そこに疲れきっている人も少なくないでしょう。
もし「今の婚活パーティーやアプリに疲れた」「条件の合う相手とは出会えるけれどピンとこない」そんな方がいれば、哲学対話を取り入れた出会い方を試してみてはいかがでしょうか。
自分自身も対話のプロセスで“変わる”感覚が得られますし、会話を通じて相手の考え方や大切にしていることがクリアに見えてきます。
婚活はゴールではなく、結婚後の人生はさらに長いもの。
だからこそ、心から分かり合えるパートナーシップを築きたい――そう願う方にとって、哲学対話という新たな選択肢は大きな手がかりになるはずです。