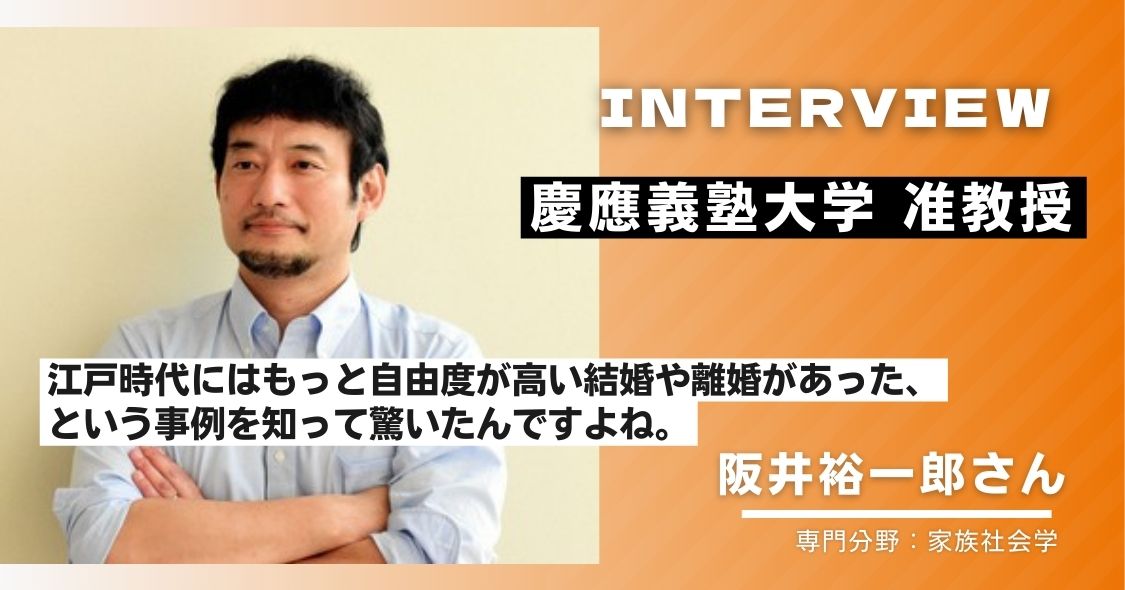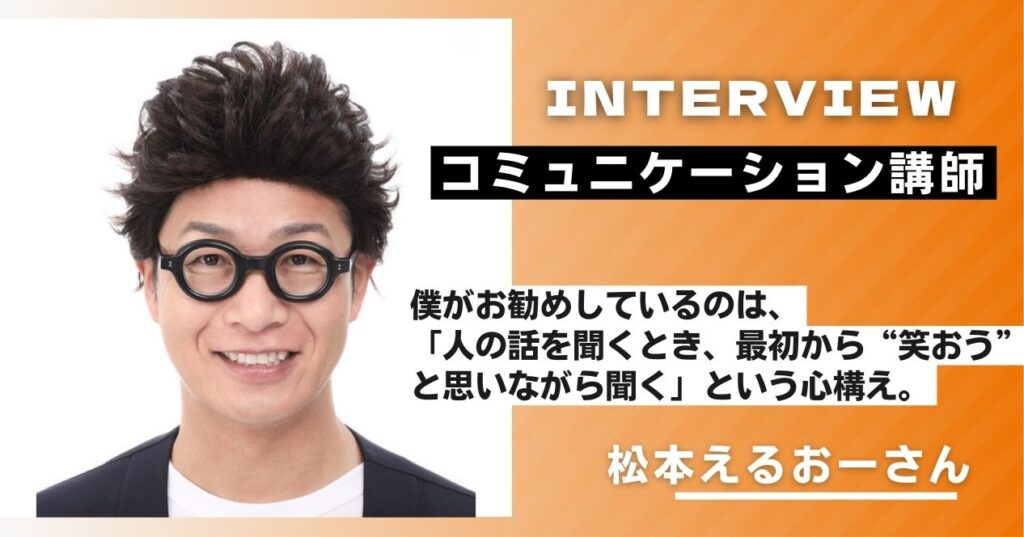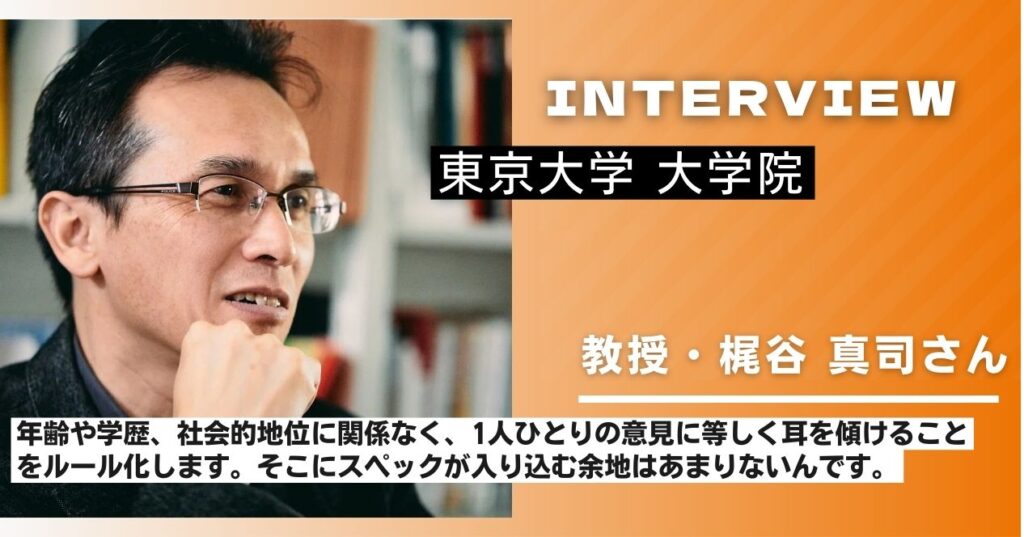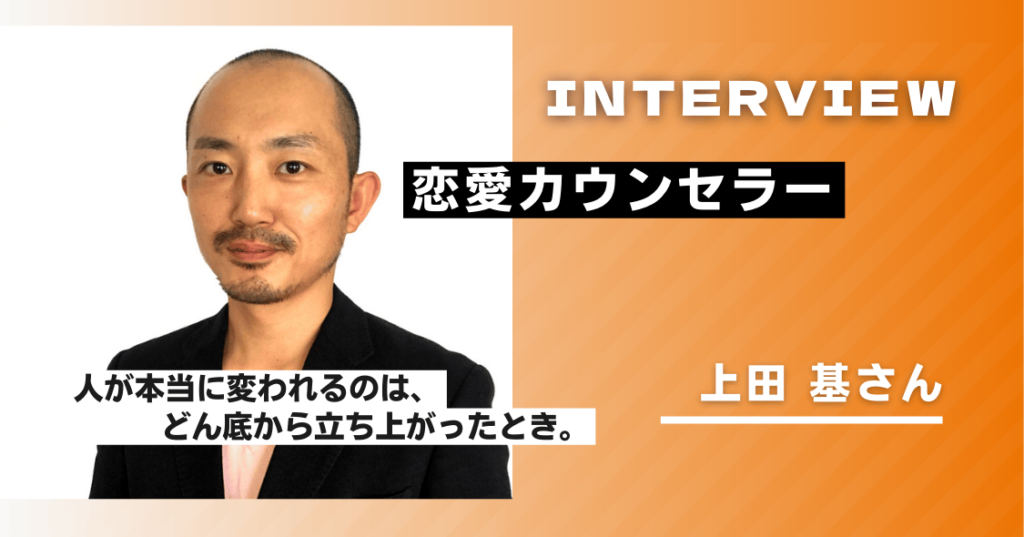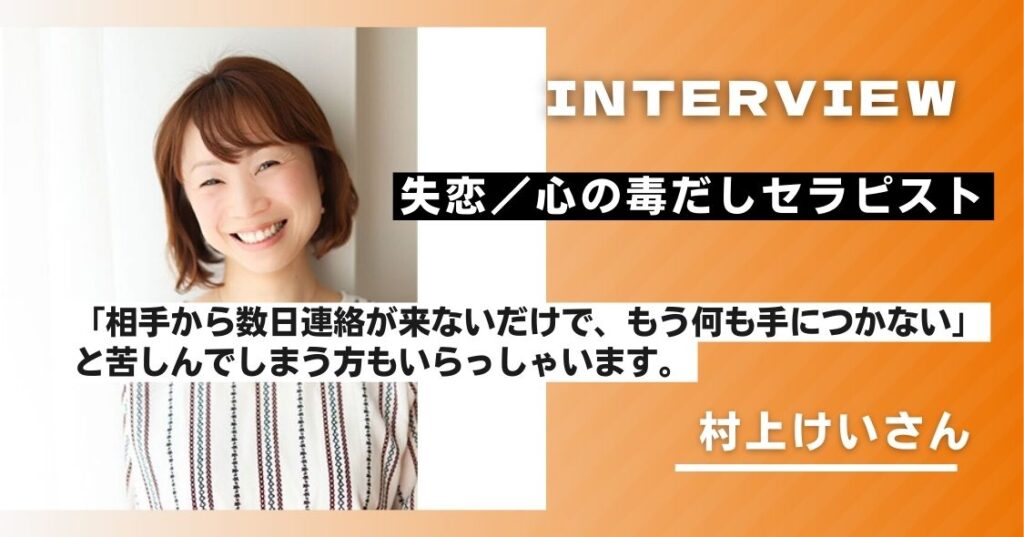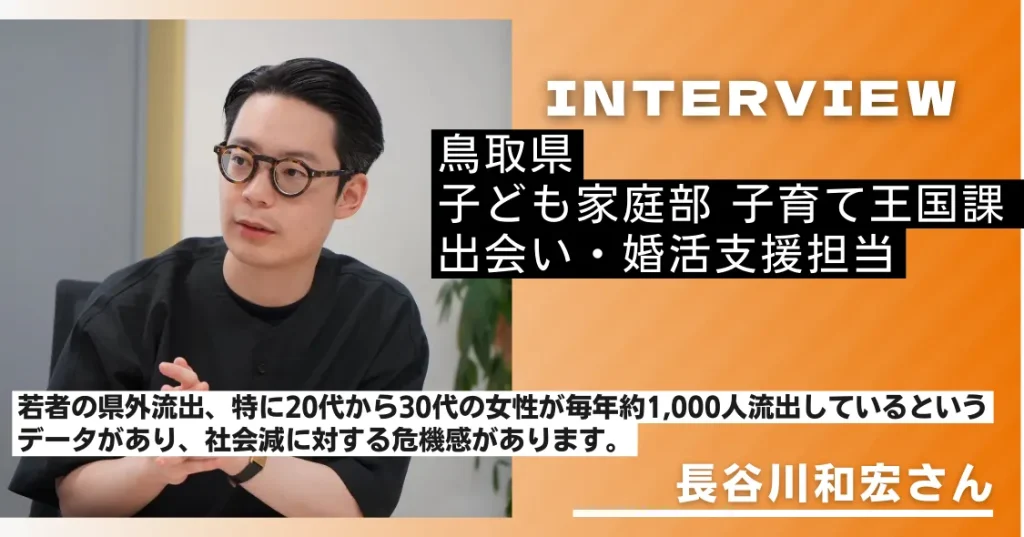結婚をとりまく社会の問題を、歴史的背景や世界の事例を通じて鋭く指摘する慶應義塾大学准教授・阪井裕一郎さん。選択的夫婦別姓や事実婚など、従来の家族観や結婚制度にとらわれない多様な価値観を研究する姿勢が、多くの若者に「結婚って本当にこうあるべき?」という問いを投げかけています。今回のインタビューでは、田舎と都会のギャップや少子化対策の本質など、婚活中の皆さんも気になるテーマを多角的にお話いただきました。

婚活パラダイス編集部 編集長
婚活パラダイス運営のLIFRELL代表取締役。自ら大学教授7名を含む婚活や恋愛に関する専門家へインタビュー取材、インタビュー数36名以上、また結婚相談所の事業者インタビューは52社、マッチングアプリ事業者インタビューは12社、利用者へのインタビューは100件以上実施。専門家から得られた知識を記事に反映しています。▶その他:執筆、編集メンバーはこちら
お問い合わせ:コンタクトフォーム
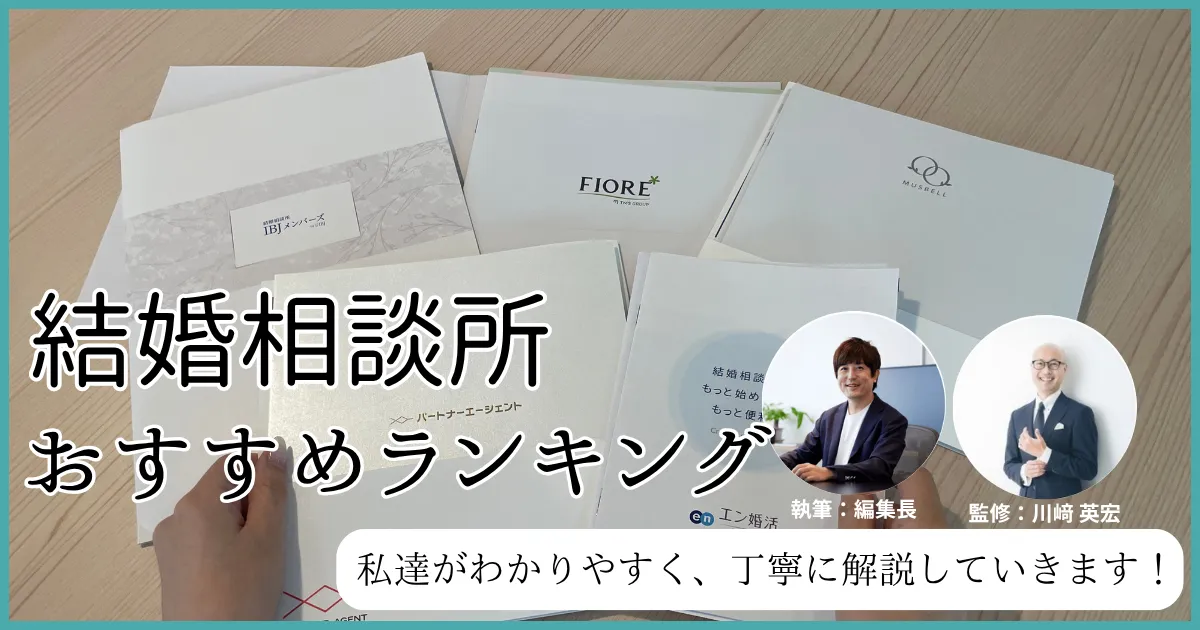
慶應義塾大学 准教授 阪井裕一郎 さん × 婚活パラダイス編集部 インタビュー

阪井裕一郎 さん
1981年、愛知県生まれ。慶應義塾大学文学部准教授。家族社会学を専門とし、夫婦別姓や事実婚など多様な結婚観の研究で注目を集める。歴史的視点から“家”と“家族”のあり方を掘り下げ、現代社会における制度や価値観に鋭い問いを投げかける。

研究との出会い・家制度への関心
–今回はよろしくお願いします。さっそくですが、先生のご著書を何冊か拝読いたしました。個人的に大変共感するところが多くて、ご連絡させていただきました。先生の書籍を拝見し、「早く社会を変えないとマズい」という危機感を感じました。
特に「結婚」をめぐる制度や常識、家制度的な価値観がいまの若い世代の現実と噛み合わず、「こんな古いルールばかりだったら結婚したいと思わなくなる」という息苦しさを強く感じていたところに先生の本を読んで、ものすごく腑に落ちたんです。
先生ご自身は、こうした家制度や夫婦別姓などの問題意識を、いつごろから強く持たれるようになったのですか?
こちらこそ、よろしくお願いします。 よく聞かれるのですが、実はこれといった“明確なストーリー”はなくて(笑)。
もともと「家制度」に関心があったんです。日本人は「無宗教だ」とか言われることも多いのですが、実際は家族や「家」という単位にすごく縛られている。
制度としてはとても古いはずなのに、現代でもある種の宗教のような力を持っているように感じました。家族社会学を学ぶなかで自然とそこに関心が向いていった感じですね。
その延長で仲人制度など「結婚」に関連する歴史や慣習、社会の変遷も調べていくうちに、「仲人がいない結婚は野合だ」みたいな言われ方をしてきた時代もあるし、「仲人を3回やるのが人生の義務」みたいな圧もあったとか、面白いなと思いながら研究してきた経緯があります。
一方で事実婚や夫婦別姓については、海外の研究事例を学ぶうちに、例えばフランスやスウェーデンでは「非婚カップルから生まれる子どもの割合」が6割以上を占めているなんていう衝撃的な事実に触れました。
日本では「多様化、多様化」と言っていても、実態を見ると全然違うのでは?という疑問が湧いたのがきっかけでもあります。
事実婚・選択的夫婦別姓の問
— なるほど。実際フランスやスウェーデンでは、もはや“結婚していないで子どもを産む”のがマジョリティになるという状況なんですね。一方、日本では「事実婚」という言葉自体、変に誤解されることも多い。
先生のご本でも「事実婚をしている人は法律婚に否定的な極端にラディカルな人だけではなく、単純に“苗字を変えたくない”から事実婚を選ぶケースが大半だ」といった実態調査が印象的でした。
僕自身も当初、事実婚を選ぶ人は「法律婚に批判的・否定的な人なのかな」という先入観があったんですが、実際にインタビューを重ねるとそうでもない。
“選択的夫婦別姓”が認められていないから、どうしても事実婚を選ばざるを得なかった、という方が多かったんですね。
そこから日本では夫婦別姓の問題に本腰を入れて向き合わないと、事実婚の実態もわからないぞと思ったのが研究の始まりでした。
— 先生の著書で「自分の苗字をくじ引きで決めることになったら男性も慌てるはずだ」というくだり、まさにそうだなと感じました。
苗字を変えることに対して、多くの男性は自分ごと化できてないだけですよね。一方で政治家の多くは60~70代の男性で、「自分とは関係ない」からずっと議論が進まない、という感想を持ちました。
本当にそうなんですよね。選択的夫婦別姓って、基本は「今までどおりの夫婦同姓を選ぶ人」はそのまま選べばいいというだけの話なのに、「どっちかが変わるのが当然」という前提から離れられない人たちが反対を続ける。もう論理ではなく宗教的な信念に近い感じもします。
しかも「子どもがかわいそう」とか理由付けもコロコロ変わりますけど、実際、離婚や再婚のときにもう一度苗字が変わってしまう方がよほど子どもに影響が大きい、という反論だって成り立つ。あまり論理的とは言えませんよね。
— そうなんですよね。「選択なんだから今まで通りがいい人はそのまま選んで」と言えばいいだけなのに、なぜか一部の方が反対している。その根本がよくわからない。
海外の方に「日本では選択的夫婦別姓がまだ認められていない」なんて説明すると、驚かれるという話もよく聞きますし……。
国際結婚や多文化間の結婚もこれからどんどん増えていくでしょうし、苗字の問題は今後、避けて通れないと思いますね。
実際、世界的に見れば「夫婦どちらかの苗字を必ず選ばなければならない」なんて国はほとんどない。
日本はOECDの中でもかなり特殊で、もう完全に議論が停滞しているように映ります。
硬直化した結婚観がもたらす問題
— 日本の結婚観は都会と地方でギャップが大きい気もします。
東京などでは「別姓? いいんじゃない?」という人が増えてきている印象ですが、地方ではまだまだ“家に入る”という言い方が当たり前で、女性がひどい例では男は夜飲みに行き、女は家で家事をしていろなんて時代錯誤も甚だしい風習が強く残っているところもある。
その結果、女性が「こんなところで結婚したくない」と言って都会に出てきてしまうんですよね。
実際、地方から若い女性がどんどん流出している現状がありますよね。
昔ながらの家制度的価値観が強い地域ほど顕著かもしれません。東京は東京で今度は家賃や生活コストが高くて「子どもを二人以上育てるのは厳しい」となる。
ある種、日本は都会も地方もそれぞれ問題を抱えてしまっていて、本当にやりづらい。そういう社会の不安定さや硬直した価値観が「結婚=リスクが高いもの」というイメージをさらに強めているように思います。
— 制度・価値観ともに古いと感じるところはとても多いと感じます。政府の少子化対策という言い方自体、どこか上から目線に聞こえるときもあって…。
予算をつけて「生んでください」と言われても、それで産みたい人が増えるわけじゃないでしょう?と思ってしまうんです。
もっと「家族政策」のようなかたちで捉えて、どうすればいろいろなカップルや家族が暮らしやすいかを考えるのが先じゃないか、と。
そうですね。実は「少子化対策」という言葉は海外ではほとんど使われていなくて、ヨーロッパの多くは「家族政策」という言い方をします。
日本や韓国、イタリアなどは昔ながらの家族や結婚制度観念が強く、「多様化しにくい」社会構造を抱えている。その結果、未婚率も上がるし、出生率が下がるという現象が起きているわけです。
経済的支援も大事ですが、それ以前に「どんな家族のかたちでもきちんと子どもを育てられる」社会にならないと、なかなかプラスに転じない。
フランスなども、先にパートナーシップや非婚出産が当たり前になって、それに合わせるかたちで政府が家族政策を充実させていったという経緯があります。
海外の事例:デンマークのエピソード
— デンマークの話も面白いですね。子どもが生まれたときに国から「あなたの子どもは、あなたの所有物ではありません。社会が面倒を見るから、何かあればいつでも頼ってください」という手紙が届くという。
そうなんです。あれは象徴的ですよね。“社会全体で子育てをサポートする”というメッセージを、親が最初に受け取る。
つまり、もしエラー(失敗)してもいいんだ、と言われることで、「とにかくやってみよう」という気持ちになれる。
日本の場合、エラーに対する許容度が低いというか、結婚や子どもを持つこと自体が大きなリスクと捉えられてしまう。
失敗したらどうしよう、という不安にばかり目が向くから踏み切れない。そういう風潮が強いのかもしれません。
ドラマやメディアによる意識変化
— ただ、ここ数年で逃げ恥(ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』)などの影響もあって、「事実婚」や「パートナーシップ」を耳にする機会は明らかに増えたように思います。
そうですね。民放ドラマやNHKの朝ドラでも、今までのような“家制度的・保守的”な価値観だけを描くのではなく、いろいろなパートナーシップのあり方を取り上げる作品が増えています。
ドラマの影響力は大きいので、ポジティブに変わってきたな、と思いますよ。
— 政府が特別何かをするのではなく、“変化の邪魔をしない”ことが大事なのかもしれないですね。海外を見ると、民衆側の動きが先に変わって、それに合わせて制度が作られたり整備されたりしている。
外圧という側面もありますね。明治時代は植民地化の恐れから条約改正を目指して西洋化・近代化を急いだし、戦後はアメリカの占領のもとで大きく社会制度が変わった。
今はグローバル経済の波が大きいですから、ジェンダーやセクシュアリティの問題に後ろ向きな企業は国際社会で相手にされない。そういう外圧によって「日本独自のやり方」も変わらざるを得ない、というのが現実だと思います。
そして実際、ここ10年ほどで民間レベルでは大きく意識も変わりつつある。もう少し時間はかかるかもしれませんが、今の政治家の上層部が引退すれば、選択的夫婦別姓や同性婚など、がらっと進むタイミングが来るかもしれません。
歴史を知ることで「気が楽になる」感覚
— 実際、先生の著書は「過去の日本史を紐解いてみると、江戸時代はもっと“ゆるい”夫婦観・離れたりくっついたりがしょっちゅうあった」という話が書かれていて、読んでいて明るい気持ちになれました。
あまりに「結婚はかくあるべし」と厳しくとらえるほど、経済的に不安な時代はどんどん萎縮してしまうんだな、と。
ありがとうございます。僕自身も「家制度の歴史」を調べていくなかで、むしろ明治期に制度化されたものが“伝統”として固定されてしまい、それ以前の江戸時代にはもっと自由度が高い結婚や離婚があった、という事例を知って驚いたんですよね。
そういう研究成果を示すと「安心した」「気が楽になった」という声もいただくことが多くて。ありがたいことだと思っています。
— これ、地方の方にぜひ読んでもらいたいですね…。まだまだ根強い古い慣習がある地域では「そういうものだから仕方ない」と思い込んでいる方が多いですが、歴史を見ると「実はそこまで昔から一貫していたわけじゃない」という気づきもあるはず。
地方の女性センターから「ぜひ話してほしい」「この本を職員に読ませたい」と言われたこともあって、やはり同じ問題意識を持っている方が多いように感じます。
新書という形でなるべく幅広い方に読んでもらえるよう意識したのも、そういった思いがありますね。
今後の研究テーマ
— 先生は今後、どんな研究に力を入れたいと考えていらっしゃいますか?
大きく三つの柱を考えています。一つは歴史研究としての「仲人」や近代の結婚制度の変遷。
もう一つは「事実婚」の研究で、これはもっと大規模にアンケート調査やインタビューを進めて、内閣府など行政機関が正確に把握できていない実態を明らかにしたいと思っています。
そして三つ目が「家族主義」の研究です。家族主義という概念には色々な切り口がありますが、「何かにつけて家族や家を優先する」という価値観が日本社会をどう縛っているのか、それがどんな領域――会社経営や福祉、住まいなど――にどう作用しているのかを整理する本を書いているところです。
理論的な内容にもなりますが、新書の形でわかりやすくお伝えできればと。
— どれもとても興味深いです。特に事実婚の実態調査は、国がやればいいのに、と思います(笑)。
「先生、事実婚って何%くらいですか?」と聞かれても、「そっちがやってくださいよ」って思いますよね(笑)。
でもそういう大規模調査はほとんどされていない現状があって。具体的に進めたいとは考えています。
— 本当にそうですよね。今回お話を聞いていても、制度やルール以前に現実は変わり始めているんだな、という明るい展望を感じられました。
先生の本を拝読してもそうですが、「古い制約ばかりじゃなくて、もっと自由に考えていいんだ」と背中を押される気持ちになります。
ありがたいですね。ドラマやメディアの影響も含めて、社会全体が少しずつ寛容になっていくことを願っていますし、実際、ここ10年くらいで確実に変化してきたと思います。
急に180度変わるわけではないですが、社会のムードは少しずつ柔軟になっているんじゃないでしょうか。
インタビュー後記
今回のインタビューでは、家制度の歴史から夫婦別姓、事実婚、地方と都会のギャップまで幅広いテーマをお伺いしました。「そもそも家制度や“伝統”と呼ばれるものも、実はそんなに長い歴史を持たない」「古くから同じ慣習がずっと続いているわけではなく、実は時代によって大きく様変わりしている」など、多くの気づきが得られたのではないでしょうか。
何より印象的だったのは、「社会が柔軟にならないと、若者が結婚に踏み切れなくなる」という示唆を得られたこと。経済的支援だけでなく、「いろんなかたちのパートナーシップを認める」「エラーを許容する」ような社会全体の意識づくりこそが、結果として出生率や家族形成に好影響をもたらす可能性が高いというお話は、多くの方に読んでいただきたい内容だと思います。
婚活パラダイス編集部としても、今後の結婚・家族に関する情報発信をするうえで、阪井先生の研究は非常に示唆に富むものでした。また新しいご研究がまとまりましたら、ぜひ続報をうかがいたいと思います。
(文責:婚活パラダイス編集部)